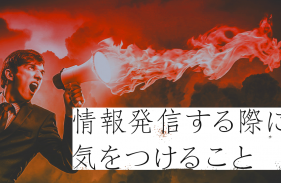10年近く前から存在しつつ、近年その価値を大きく変えはじめているライブ配信。ここ数年で勢力図は大きく変わりInstagramやFacebook、SHOWROOMやLive.meなど多種多様なライブ配信サービスが日本にも登場してきています。
グローバルでの動画サービスの台頭や中国でのVideoコマースの影響、インフルエンサーの台頭と言った要因は複合的にありつつ、プラットフォーマーも数多く登場。それぞれで得意とするポジションをおさえるべく、しのぎを削っています。
今回はそんな動画配信プラットフォームの中でも、国内では圧倒的なシェアを誇るメッセンジャーサービスLINEが手がける『LINE LIVE』に注目。同サービスを担当する浅野裕介氏にお話を伺い、LINE LIVEの強みと特徴、今後の展望を伺いました。
プロフィール
浅野裕介氏
LINE株式会社 エンターテイメント事業部 ビジネス開発統括責任者
縦も横もコミュニケーションが生まれるLINE LIVE
大久保:LINE LIVEについて簡単にご説明いただけますでしょうか。
浅野: LINE LIVEはライブ配信のプラットフォームです。これまでの映像プラットフォームは、事前に作成した映像を流し、そこに対して視聴者が反応するという一方通行のコミュニケーションでした。一方、LINE LIVEでは録画ではない今の映像を配信し、その場で視聴者がコメントをするという双方向のコミュニケーションが生まれています。
非常に面白いのは、配信者と視聴者の縦のコミュニケーションはもちろんのこと、視聴者同士の横のコミュニケーションも生まれていることです。この2軸のコミュニケーションがクロスし広がっていく。ときには配信者を置き去りにして、視聴者同士で盛り上がっていることも少なくありません。これはいままでの映像プラットフォームにはないひとつの文化だと思っています。
大久保:たしかに、いわゆるこれまでの配信でも縦の関係性がメインでした。それに横が加わると。
浅野:この横のコミュニケーションはここ数年のムーブメントでもあります。たとえば映画『シン・ゴジラ』には、発声可能上映というのがありました。名前の通り、声を出していい上映会です。映像の中で何かが起こると、それに観客が突っ込む。そこで誰かがおもしろいことを言うと、周りの人たちが今度は自分が言いたくなるんです。その場にいる人によって反応が変わるので、一度として同じ上映会はない。
たとえば予告編で『君の名は。』が流れた時に、『前前前世』を歌い出すとか。一人歌い出すとみんな歌い出す。すると、さらにおもしろいことをやろうと考える。映像はきっかけでしか無く、そこにあるのは横のつながりなんです。
参考:http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/090200078/090700019/
大久保:LIVEであること、かつ横のつながりが生まれる場だからこその楽しさが存在するということですね。それをLINEさんとして行う上での強みはどこにあるのでしょうか?
浅野:わかりやすい点は、LINEならではの身近なコミュニケーションです。現在LINE LIVEを観ている方の9割以上はLINE IDでログインして観ているので、LINEで友人にコミュニケーションをとる延長上にLIVEがある感覚を持っていただける。相手にスタンプを送ったり、メッセージを送るように気軽にコメントをするなどというのは、LINEのプラットフォームならではのものです。
こういったコミュニケーションはLINE LIVEのユーザー層にもマッチしています。今のLINE LIVEのコアユーザーは10代の若年層で、いわゆるZ世代と言われる人々です。彼らはリアルで、作られた感がないものを求めている。そういう意味でリアルなコミュニケーションの延長上にあるLINEもLIVEも相性がいい。
ですから我々もありのままの日常を自然に見せるよう気をつけています。たとえば、後ろの背景に物を設置したり、演出するのは彼らにとってはマイナスです。視聴者からすると、スマホで観るのは作られたものでなくビデオ通話の画面に近い。その日常から少しでも離れると、求めているスマホの映像では無くなってしまうのです。

広告の可能性を拡張する配信の価値
大久保:LINE LIVEでは、どのようなビジネスモデルを構築されているのでしょうか。
浅野:個人のギフトと動画広告がメインの収益源です。ギフトはLINEの延長上で、スタンプやハートなどが現状LINE LIVEのポイントで贈れるので、そこでマネタイズをしていくものです。
一方動画広告は、動画再生前に流れるインストリーム広告を導入しており、スマホならではのエンゲージメントが高いLINE LIVE独自のものを検討しています。LIVEのユーザーはCM中もコミュニケーションを取り、CMに対してコメントをしあうんです。たとえば以前に「さしめし」というオリジナルコンテンツで、フード系のクライアントさんに出稿いただき、番組内でそれを食べつつ、CMでもその食べ物の広告を流しました。
するとユーザーが「美味しそう」という印象を抱き、配信画面をスクショして、SNSへ投稿していました。しかも「美味しそう」「今日これ食べたい」とコメントをつけてです。出稿する企業からすると、ブランド訴求と、ユーザーがリアルにどんな反応をしているのかが目に見えるメリットがあります。
大久保:リアルタイムに反応することが当たり前になっているので、エンゲージメントも高いと。
浅野:おっしゃるとおりですね。縦と横のコミュニケーションを阻害されない広告に対して視聴者は非常に好意的に捉えていただける。我々は、ここに動画広告の未来があるんじゃないかと考えています。一方こういった広告の収益は配信者さんへも還元される仕組みを作っていかなければいけない。
将来的には配信者さんが、配信中に席を外すときに「ちょっと待っててね」とCMを流すなんてこともあるかも知れません。コミュニケーション手段として、配信者さんが流したいCMを流す。視聴者側も待機しつつ、コメントする。配信者側・ユーザー側双方にとってのコミュニケーションツールのひとつが広告になるというイメージです。そういった可能性も現在模索しています。

「雑談」というカテゴリが持つ可能性
大久保:現状さまざまな配信サービスが存在しますが、LINE LIVEの配信はどんな特徴があるのでしょうか?
浅野: LINE LIVEの特徴でいうとやはり「雑談」のような配信でしょう。配信者さんはとくに何をするでもないんです。「何々さんいらっしゃい」って名前を呼んで、コメントを元に会話をする。それで配信が成立しているんです。それを丁寧に細かくできる方が、ランキングの上位に上がってきます。一般的には歌が歌えたり、見栄えが良いといった一芸がある人が強いと思われますが、雑談はそうではない。
それ以上に自分を呼んでくれる人。「何々さん、何日ぶりだね、この前どうだった?」みたいなことを自然と言えて、コメントが流れる中でもコメントをしっかり返す能力を持っている人が強いです。雑談が究極のコミュニケーションだからこその現象だと思います。
大久保:なるほど、雑談となると一般的な配信者とはだいぶ異なるスキルになりそうですね。では、個人配信者の中で、LINE LIVEで活躍されている方はどういった人になるのでしょうか。
浅野:平たく言えばリアルであること、そしてマメであることでしょう。これは先ほどのZ世代の特徴とも絡んでくるのですが、やはり日常やリアルをそのままさらけ出して会話できる人が活躍します。
そして、寄せられるコメント1つひとつに対してちゃんと返したり、ありがとうと言える人。さらに、ライブ配信後にTwitterなどで、LIVE中に言えなかったお礼とかを言える人。
具体的にいうとハートランキングをキャプチャして、「今日はありがとう」とコメントしたり、Twitterでリプがきたら返したり。コミュニケーションをしっかりと取っている人ほど人気を集めやすいです。
大久保:LIVEだけでなく、オンラインのあらゆる場でコミュニケーションをしっかりととれる人ということでしょうか。
浅野:彼らからするとLIVEさえも手段でしかないのだと思います。今の若い世代は常にLINEを立ち上げていて、つながっている状態です。ですからLINE LIVE自体も、どんどん配信時間を延ばして、常時つながっているといった世界観の方がイメージとしては近いのかも知れません。常につながってコミュニケーションできることの価値が、今後どんどん増すのでしょう。
Z世代が配信する2つの理由
大久保:配信者の方はどういった動機で配信しているのでしょうか?何か一芸を披露するためというのであればわかるのですが、日常となるとイメージがわきづらいなと。
浅野:主に2つあります。1つは、配信をきっかけに有名になれれば、チャンスがあるんじゃないか、タレントになれるんじゃないかといった承認欲求が起点の人。もう1つは、隙間時間があるときに誰かとコミュニケーションしたいなと思ってやる人。後者の方は、コミュニケーションを取ること自体が目的になっている。
たとえば、バイト上がりにLINEとかで「疲れたよ」というメッセージをカップルや家族とするように、LINE LIVEの世界でする。音声と映像があると温かみは一気に増します。その温かさに触れたいというのは人の本来の欲求だと思うんです。そういった何気ない話し相手を見つける場として機能しているのかなと。
大久保:後者の人は、継続的に配信していくんですか?
浅野:そういった動機の方が、毎日配信されています。日常なので、歯を磨くのと同じような感覚でLIVEをするんです。本当に付けておくだけ。ただ視聴者さんからすると、自分の名前を呼んでくれるのがすごく嬉しいんですよね。

グローバルをつなぐプラットフォームを目指して
大久保:非常に興味深い使われ方でありつつ、継続的に使ってもらえる動機もある。さらに、そこに配信する広告も高いエンゲージメントを狙いやすい。プラットフォームとしてはとても可能性があるのかなと思いますが、今後の展望としてはどういったところになるのでしょうか。
浅野:ビジネス面でいうと、グローバル展開の強化ですね。LINE自体もグローバル展開を強めていますし、LINE LIVE自体もグローバル展開は行っています。ですが、まだまだこれからな市場なので今後さらに強化していきたい。
その結果として、より世界の距離を縮められればと思いますね。パソコン通信やらPCでのインターネットの時代と比べ、スマホになったことで人同士の距離はより縮まったと思います。それがLIVEの常時接続で、世界とリアルタイムに繋がっている状態が実現できると世界はより小さくなるなと思っていて。
これまでは、1つの地域の人で閉ざされていた世界が、ネットワークを通して他の地域の人と繋がっていく。そこで新たな価値やチャンスが生まれるかも知れない。そういった可能性の輪を広げられるような役割を担っていきたいです。
インフルエンサーラボ創刊編集長。企業向けのSNSマーケティング情報発信メディア、ソーシャルメディアラボ( https://gaiax-socialmedialab.jp/ )の編集長も務める。
-
インタビュー
 インフルエンサー自身の「なりたい」を大事にする。『Coupe』のインフルエンサーとの向き合いかたとは
インフルエンサー自身の「なりたい」を大事にする。『Coupe』のインフルエンサーとの向き合いかたとは -
インタビュー
 関西トップダンサーTOMOに聞く、リアルが大事なパフォーマーだからこそのSNSとの向き合いかた
関西トップダンサーTOMOに聞く、リアルが大事なパフォーマーだからこそのSNSとの向き合いかた -
インタビュー
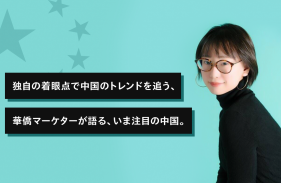 独自の着眼点で中国のトレンドを追う、 華僑マーケターが語る、いま注目の中国。
独自の着眼点で中国のトレンドを追う、 華僑マーケターが語る、いま注目の中国。 -
インタビュー
 インスタ開始1年半で、フォロワー26万人超え。浮世絵スタイルの「あるある」が大人気、山田全自動ができるまで
インスタ開始1年半で、フォロワー26万人超え。浮世絵スタイルの「あるある」が大人気、山田全自動ができるまで -
インタビュー
 発信力やコミュニティは個人の無形資産。ビジネスモデル図解のチャーリーさんが語る「コミュニティ観」
発信力やコミュニティは個人の無形資産。ビジネスモデル図解のチャーリーさんが語る「コミュニティ観」 -
インタビュー
 誰もが自分のアバターを配信できる世界へ。話題のバーチャルライバーの真実に迫る。
誰もが自分のアバターを配信できる世界へ。話題のバーチャルライバーの真実に迫る。